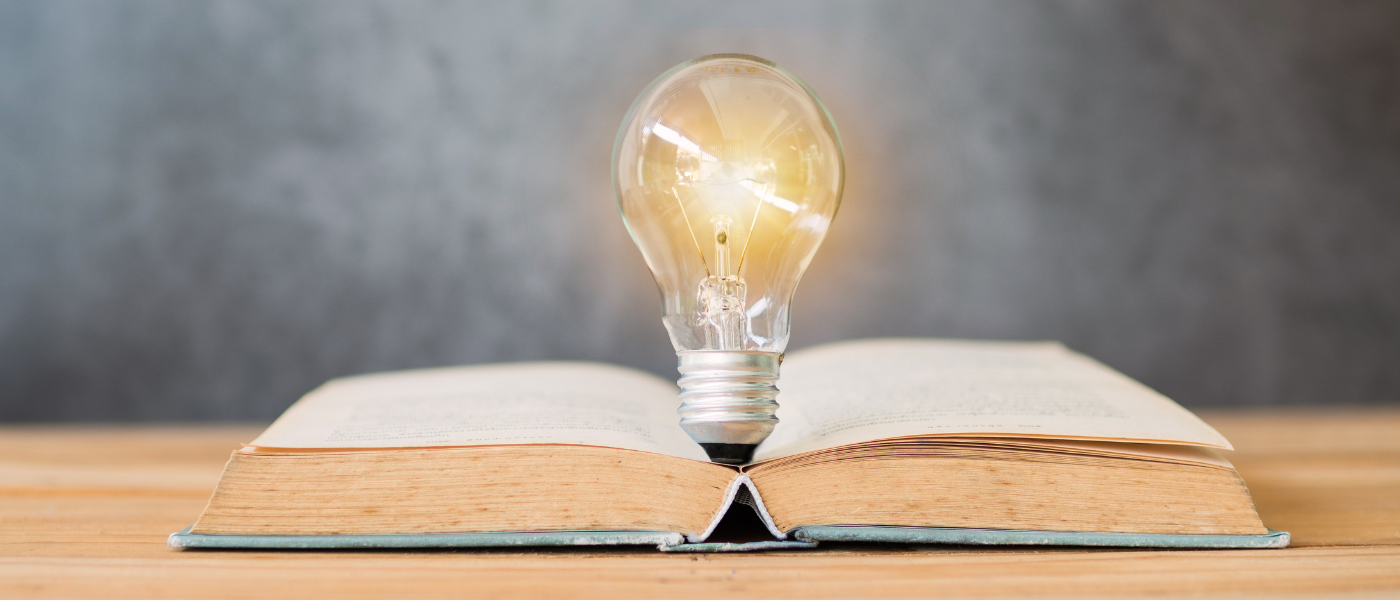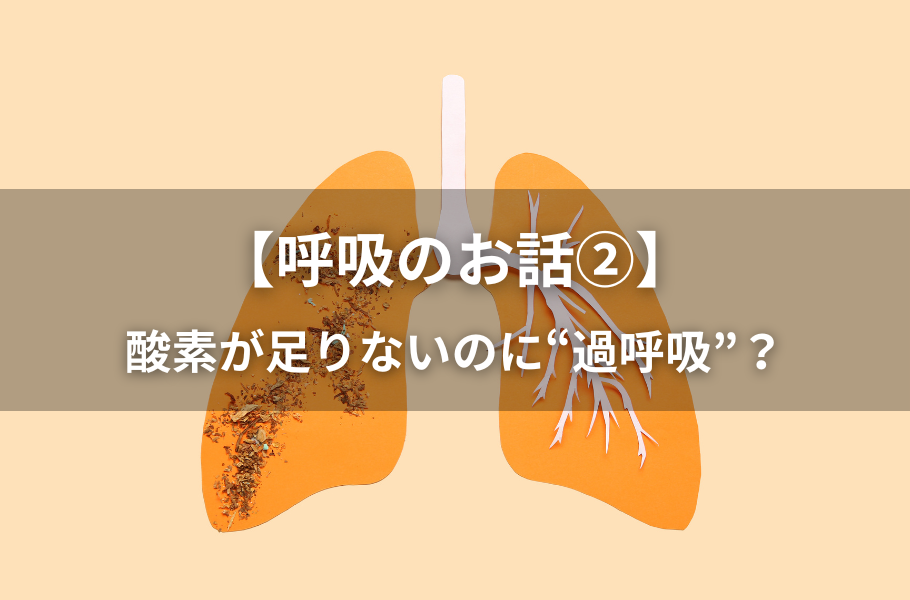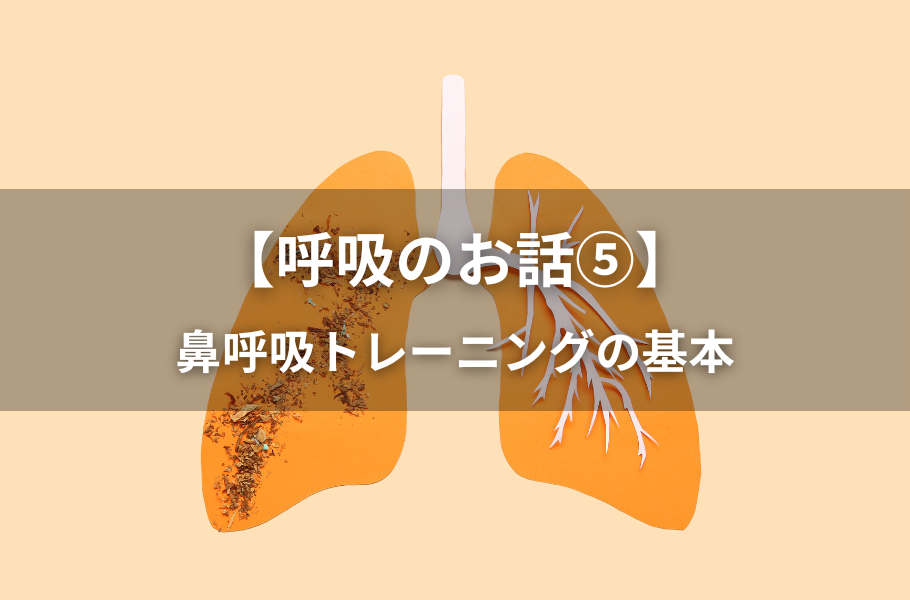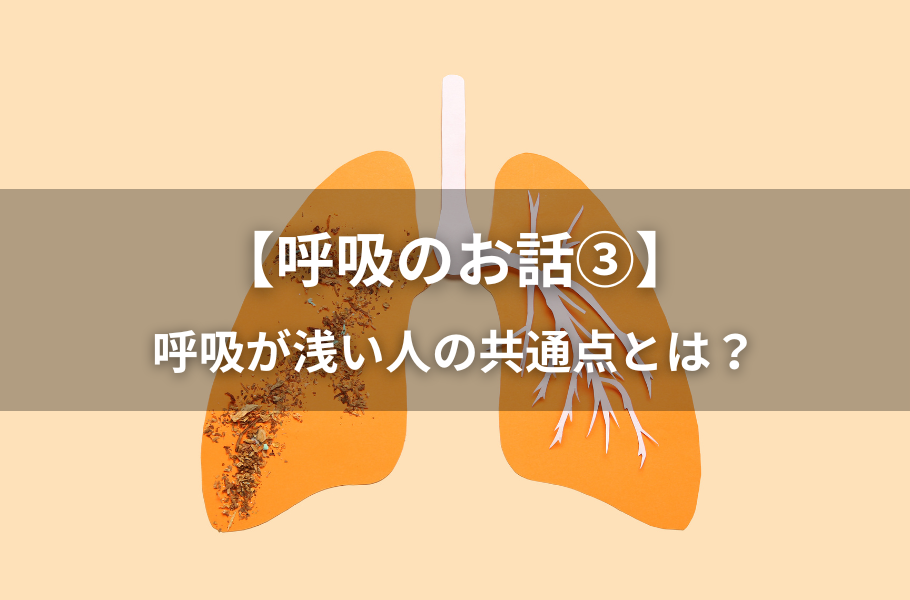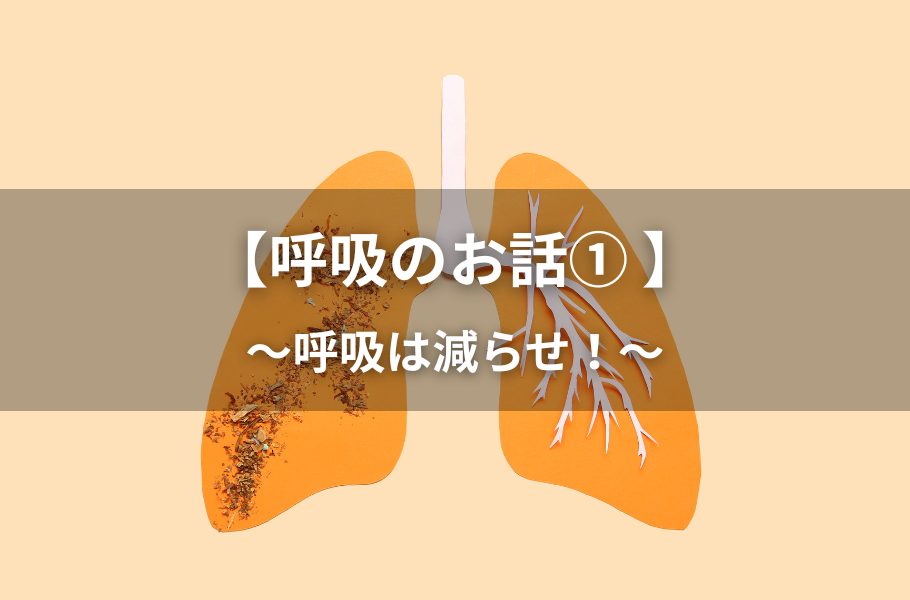博多駅から徒歩8分
からだ想い整体院めぐりの鈴木です。
今回は「酸素が足りないのに“過呼吸”?」という、一見矛盾したようなテーマでお話しします。
「息苦しい」「酸素が足りない気がする」と感じると、多くの人は反射的に“もっと吸おう”とします。
でも実は、その「たくさん吸う」行為こそが、体をさらに“酸欠状態”に追い込んでいるのです。
「過呼吸」ってどういう状態?
「過呼吸」とは文字通り、“呼吸をしすぎる”こと。
不安やストレス、緊張、姿勢のくずれなどによって呼吸が浅く速くなり、体が必要とする以上に空気を出し入れしている状態です。
呼吸をたくさんすると、肺にはたくさんの酸素が入ります。でも、その分だけ体内の二酸化炭素(CO₂)がどんどん排出されてしまう。
実はここが大きな落とし穴。
CO₂が減りすぎることで、血液中のpHバランスが変化し、酸素が“細胞に届かない”状態になるのです。
酸素があるのに使えない?その理由
血液の中では、酸素は「赤血球のヘモグロビン」にくっついて運ばれています。
その酸素を手放すスイッチとなるのが——CO₂の存在。
CO₂が適度にあることで、ヘモグロビンが酸素を細胞に渡しやすくなる。この仕組みを「ボーア効果(Bohr effect)」といいます。
ところが、過呼吸でCO₂が減ると、ヘモグロビンが酸素を離さなくなり、血液中には酸素が十分あっても、筋肉や脳には届かない“隠れ酸欠”が起こります。
結果として、体は「酸素が足りない」と感じて、さらに呼吸を増やしてしまう——。
これが、過呼吸の悪循環です。
息苦しさ=「酸素不足」ではなく「CO₂不足」
多くの人が「息苦しい=酸素が少ない」と誤解しています。
実際はその逆で、CO₂が少なすぎることが原因の場合が多い。
CO₂が少なくなると、
血管が収縮して脳への血流が減り、めまい・手足のしびれ・頭のボーッと感などが出てきます。
つまり、「息苦しさ」は酸素を吸えない苦しさではなく、酸素を届けられない苦しさなのです。
なぜ現代人は過呼吸になりやすいのか
現代人の生活環境は、過呼吸を起こしやすい条件がそろっています。
-
デスクワーク中心で胸郭が固まりやすい
-
ストレスや不安で交感神経が常に優位
-
口呼吸の習慣(鼻呼吸の機能低下)
-
スマホ姿勢で頭部が前に出ている
これらはすべて「浅く速い呼吸」を助長します。
つまり、呼吸の“質”が低下し、CO₂を保持できない状態です。
過呼吸を防ぐための第一歩:「吐く」と「止める」
呼吸を整えるには、「吸う」よりも「吐く」こと。
そして、吐いたあとに少し“止める”ことが鍵になります。
この「止める」フェーズが、CO₂を体に残す時間をつくり、ヘモグロビンが酸素を細胞に渡す余裕を生み出します。
🟢 5-5-5呼吸法(慣れたら10-10-10へ)
-
鼻から 5秒吸う
-
口から 5秒吐く
-
吐いたあとに 5秒止める
「止める」時間をつくることで、CO₂への耐性が少しずつ高まり、“吸いたい衝動”をコントロールできるようになります。
続けていくと、呼吸の回数そのものが減り、一回の呼吸がゆったり深くなる。
その結果、脳も筋肉もリラックスした状態が保ちやすくなります。
👉 関連記事:【呼吸のお話】呼吸は減らせ!
「過呼吸体質」から抜け出すために
過呼吸は一時的な現象ではなく、日常の「呼吸習慣」が形づくった体のクセです。
-
緊張すると肩が上がる
-
常に胸が動いている
-
呼吸を止めるのが苦手
こうした特徴がある人は、CO₂耐性が低く、呼吸のコントロールが苦手になっています。
焦らず、「鼻で吸う・長く吐く・止める」を意識して、1日数分でも続けることが重要です。
呼吸の質が変われば、自律神経・姿勢・睡眠までも整っていきます。
まとめ:吸うより、届ける呼吸へ
「息苦しい」ときほど、吸うよりも“静かに吐く”こと。
呼吸は量ではなく、届ける力が大切です。
CO₂を敵ではなく味方にすることで、呼吸は穏やかに、そして効率的になります。
たくさん吸うより、静かに整える——。
それが、本来の呼吸のリズムなのです。
🧩 関連記事(呼吸カテゴリー)
\ 初回限定クーポンで初回体験を予約する /
(ホットペッパーで予約)
あなたのオススメのクーポンはこちら
博多からだ想い整体院めぐり
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目12-3
玉井親和ビル 3-B
執筆者:鈴木 貴英(柔道整復師・トレーナー)
呼吸と動作の再教育を専門とし、慢性痛・自律神経・姿勢改善にアプローチ。
「体の感覚を取り戻す」ことをテーマに、心身の調和をサポートしています。